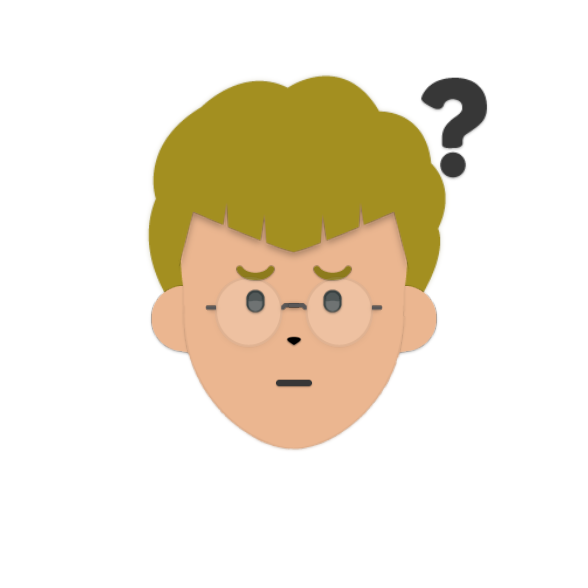
悩めるお兄さん
行政不服審査法37条の審理の計画的遂行がよく分からない‥
試験対策もあれば一緒に教えて欲しい。
そんな悩みに答えます。
本記事で分かること
- 行政不服審査法37条の「計画的遂行とは何か」が分かる
- 行政不服審査法37条の「試験対策」が分かる
- 過去問を解いて「理解度」を深められる
※0円で学ぶオンライン講座という近道
最近はオンラインで学べる予備校も増えており、忙しい社会人にはstudyingの方が早く学べるかもです。 studyingは5回分の無料体験講座があるので、これを使って基礎を学ぶのもありですね。
»studyingの無料講座はこちら
最近はオンラインで学べる予備校も増えており、忙しい社会人にはstudyingの方が早く学べるかもです。 studyingは5回分の無料体験講座があるので、これを使って基礎を学ぶのもありですね。
»studyingの無料講座はこちら
行政不服審査法37条:計画的遂行とは【分かりやすく解説】

計画的遂行とは
審査請求の審理事項が多数な場合や、複雑な場合は「審理関係人で集まって計画的に進めましょう〜!」という規定です。
不服審査法の目的条文である、簡易迅速を図るためですね。
【審理手続の計画的遂行】
1 審理員は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜しているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、第三十一条から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。
試験対策
選択肢の文末が「しなければならない」と義務になっていたら誤りと判断しよう。
「申立人は」とか「審理関係人は」などに入れ替えてくるので注意
31条2項(口頭意見陳述)の規定では、「全ての審理関係人を召集する」とあるが、37条は「審理関係人を召集し」にとどめた条文なので、混在しないように注意しましょう
<試験対策まとめ>
- 文末に注意:することが「できます」と任意
- 実行できるのは「審理員」のみ
- 召集は全員ではない
過去問:レッツチャレンジ!(2問)
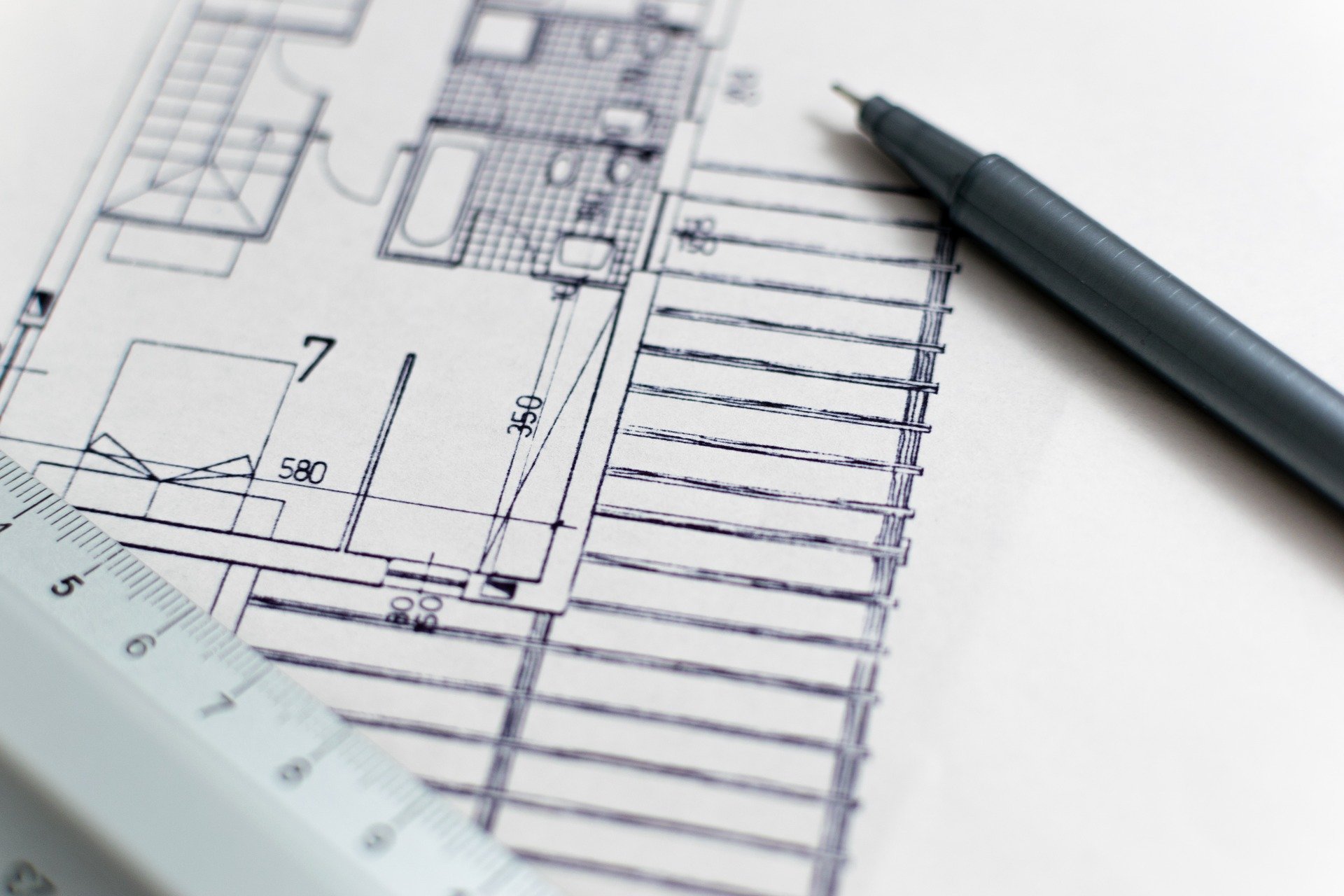 (問題文長いけど頑張ろう‥)
(問題文長いけど頑張ろう‥)
Q.審査請求人又は、参加人は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又は錯綜している事件などが複数であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、審理手続きを計画的に遂行する必要があると認めた場合には、審理員に対して、期日及び場所を指定して、審理関係者を召集し、あらかじめ、これらの申し立てに関する意見の聴取を行うことを求めることができる
×
「審理員」は審理関係者を召集することができます。
よって、審査請求人や、参加人は召集することができません。
「審理員」は審理関係者を召集することができます。
よって、審査請求人や、参加人は召集することができません。
Q.審理員は、審査請求に係る事件について、審査手続を計画的に遂行する必要があると認める時は、期日及び場所を指定して、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができるが、この場合、全ての審理関係人を召集しなければならない
×
文末の「全ての審理関係人を」が誤りですね。
37条1項では、「審理関係人を召集し」と記載がありますが「全ての」の記載はありません
文末の「全ての審理関係人を」が誤りですね。
37条1項では、「審理関係人を召集し」と記載がありますが「全ての」の記載はありません
、;l




コメント